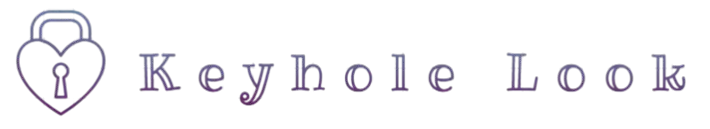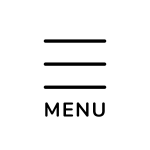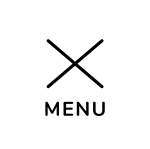お辞儀の謎!日本の礼儀作法、角度や歴史、現代での意味とは?お辞儀の起源から現代での使用まで、徹底解説!
古くは神への敬意から、現代では人間関係を円滑にする日本の「お辞儀」。番組とgoo辞書が紐解く、その奥深い歴史と多様な意味合い。飛鳥時代に中国から伝来し、武士の台頭、礼法の発展を経て、敬意、挨拶、そして遠慮を表す言葉へ。角度による分類、時代ごとの作法、さらに「おじ」という言葉の多様な使われ方まで。日本文化を象徴する「お辞儀」の真髄に迫ります。

💡 お辞儀は、相手への敬意や敵意がないことを示す日本の挨拶の基本動作で、角度によって意味が異なる。
💡 お辞儀の起源は中国の礼法にあり、時代とともに意味合いが変化し、現代の形へと進化を遂げた。
💡 正しいお辞儀の作法を理解し、ビジネスシーンや日常生活で適切に使い分けることが重要である。
それでは、お辞儀の歴史と文化、そして現代における意味について、詳しく見ていきましょう。
お辞儀のルーツを探る旅
お辞儀の起源は?いつごろ日本に伝わった?
中国の礼法が起源。飛鳥〜奈良時代。
お辞儀の起源と歴史について紐解いていきましょう。
公開日:2020/11/04

✅ お辞儀は、相手への敬意や敵意がないことを示すために行われる日本の挨拶の基本動作で、飛鳥〜奈良時代に中国の礼法が取り入れられたのが始まりです。
✅ お辞儀は立礼と座礼があり、角度によって会釈(15度)、敬礼(30度)、最敬礼(45度)と分類され、それぞれ異なる場面で使われます。
✅ お辞儀の語源は「時宜」であり、江戸時代後期に挨拶で頭を下げる動作に限定されるようになるまで、物事の適切な時期や状況を表す様々な意味合いを持っていました。
さらに読む ⇒歴史・文学会館出典/画像元: https://reki-bunkaikan.com/2020/07/09/%E3%81%8A%E8%BE%9E%E5%84%80/なるほど、お辞儀は単なる動作ではなく、深い歴史的背景と意味合いがあるんですね。
時代とともに変化してきたという点も興味深いです。
お辞儀は、世界中で見られる普遍的な行為でありながら、日本のように日常的に行われる文化は独特です。
その起源は、神への敬意を示す行為として古くから存在していました。
番組とgoo辞書の情報から、お辞儀は飛鳥〜奈良時代に中国の礼法が起源とされ、平安時代末期の絵巻物には既にお辞儀の原型が描かれていました。
元々は、季節や時期に応じた挨拶である「時宜」に由来し、時代とともに意味が変化を遂げ、「辞儀」へと変化しました。
そして、敬意を示す接頭語「御(お)」が加わり「御辞儀」となり、敬語表現として定着しました。
へー! 中国の礼法がルーツなんだ! なんか意外! 時代劇とかで見るあれだもんね。それにしても、時宜って言葉の意味合いから来てるってのが、なんかオシャレ!
武士道とお辞儀の進化
武士社会で重要になった「お辞儀」の役割は?
敬意を示す手段、人間関係の潤滑油。
武士道と礼法が密接に結びついているんですね。
公開日:2022/09/01

✅ 小笠原流礼法は、約800年以上続く武家の礼法を基本とし、体や物の機能を理解した合理的で美しい所作を特徴としています。
✅ 礼法は、単なる形式主義ではなく、所作の「理(ことわり)」を理解し、呼吸と動作を一致させることで、自分で考える力や品格を育むことを目的としています。
✅ 親子で学べる礼法の動画も公開されており、お辞儀、立ち方、座り方、ドアの開け方、食事の仕方など、日常で活かせる基本の所作を学ぶことができます。
さらに読む ⇒婦人画報デジタル食も文化もウェルネスも。「本物」がここにある出典/画像元: https://www.fujingaho.jp/lifestyle/manner/a40803585/ogasawara-20220901/武士道精神を反映した礼法、奥が深いですね。
所作の『理』を理解するというのは、現代にも通じる考え方だと思います。
鎌倉時代になると、武士が台頭し、身分制度が確立。
これに伴い、お辞儀は人間関係における敬意を示す手段として重要な役割を担うようになりました。
武家社会では、小笠原流のような礼法が生まれ、場面や相手によって九品礼など使い分けられました。
「おじき」という言葉は、親しみを込めて「おじ」を指す言葉としても使われました。
また、「御直」を意味し、貴人が自ら直接行うこと、または「御直衆」の略称を指す場合もありました。
小笠原流って、なんかカッコイイ! 動画で学べるってのもいいね! 推しの舞台挨拶とかで、この礼法使ってる人いるかなー?チェックしよ!
次のページを読む ⇒
お辞儀の作法を徹底解説!角度で変わる敬意、時代ごとの変化、多様な意味合い。言葉のルーツを探り、現代社会での役割を紐解きます。